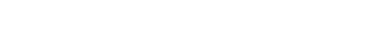歴史
本文
歴史めぐり
糠塚古墳
豪族の墓である糠塚古墳は太郎布高原にあり、直径30m、高さ5mの円墳で7世紀頃のものといわれています。 横穴式の古墳と考えられており、頂上に載せられた巨大な川原石(蓋石)の直下には地方豪族の遺体を収めている石室があるはずですが、この石室に通じる道が埋没しているため、確認されていません。
中丸城跡
中世の400年間、この地方を支配した山ノ内氏は本拠地として横田を選び、鷹の巣山に山城を築いて中丸城と名付けました。中丸城の頂上は547mで、天険を利用した要害の山城ということができます。頂上の本丸の平地には現在も摩利支天がまつられていますが、山ノ内氏の軍神として尊ばれたものです。 最後の城主は山ノ内氏勝ですが、豊臣秀吉の会津下向により領土を没収され、越後大浦で死去したため、氏勝の墓は下大浦の延命寺にあります。
磨崖仏群
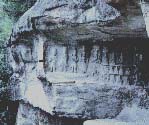
鮭立集落の背後にある細長い洞窟の中に、会津地方でただ1ヶ所の磨崖仏群があります。不動明王を中心とした大小さまざまの、51体の仏像は、修験者によって200年程前から数十年の歳月をかけて、五穀豊穣、病苦退散を祈って彫られたものです。 全面の幅がおよそ5m、高さ2m、奥行きは浅く1,5程度の洞穴の壁面に彫刻されたもので、規模は小さいのですが、製作当時は各体に顔料を施し、大変美しい磨崖仏だったと考えられます。
聖観音坐像

宮崎大悲堂に鎌倉の中期の作と言われる、寄木づくりの聖観音坐像があります。ふくよかで優美な姿は平安末期の様式の流れを汲むものといわれ、この観音像をこの地に招聘して崇敬した文化的な人々の姿があったことと思われます。
| 本体 | 木造(ヒノキ)寄木造りで、全体に漆箔が施されていました。像高は99.5センチで、いわゆる等身像です。条帛をかけ天衣が両肩を覆っています。両手は屈臂して胸前に構え、左手は掌を内にして五指を曲げ、持物(半開の蓮華)をとり、右手は掌を前にして立て、印を結んでいます。また、裳をつけ腰布をまとい、結跏趺坐しています。 なお、髪型は高い宝髻(15.3センチ)で、一束の髪が左右の耳朶を巻いており、顔面は輪郭が円みを帯び、藤原末期(平安時代の末)の顔貌に似ているところさえあります。また目は玉眼を嵌め、あごは二重あごでやわらかい曲線を画いています。次に胸部は引きしまってふくらみがあり、腹部はみぞおち部がはっきり表現され、下腹部はほどよくふくらんでいます。 |
|---|---|
| 光背 | 輪光背で、その直径は69.2センチ、用材はヒノキで寄木造り、漆箔が施されています。 |
| 台座 | 蓮華三重坐で高さ30.8センチ、用材はヒノキ、寄木造り、漆箔が施されている点、本体同様です。 |
旧五十島家住宅
江戸時代中期に建てられたもので、当時の標準的民家の平屋中門造り(注)です。こぶし館の隣りにあります。



概略
- 1.柱
- 高さはわずか十尺で低く、礎石に直接立てる「石場立て」である。
- 2.屋根
- カヤ葺きの寄せ棟で、中門は本屋よりやや低い。
- 3.間仕切り
- ・三間取りの広間型である。
- ・二間は板敷きで、表側の一間は主として冠婚葬祭に使用し(ザシキ)、裏側の部屋は主人夫婦の寝室(ヘヤ)にあてる。
- ・土間はすべてタタキである。
そのうち7坪半は居間(チャノマ)で、ほぼ中央に炉を設けて火棚と自在カギをつけ、炊事場、食堂、接待室を兼ねる。さらに8.75坪はわずかに低くして作業場(ニワ)にした。 - 4.その他の特質
- ・ザシキとヘヤのほかは一切戸や障子を用いず、内部はきわめて開放的である。
- ・柱その他の構造材はすべて雑木(栗)を用い、仕上げは斧またはチョウナで、カンナは使用していない。
- ・天井には太くて長い雑木(栗)を2本つなぎ、これを「中引き」とし、梁を固定している。
- ・外部は壁が多く、全く閉鎖的で暗い内部となっている。
- ・屋根下はサスで合掌形につくり、垂木は加工しない細木を用い、モヤに縄で緊縛している。
- ・天井には裏板を張らず、化粧屋根裏としている。
(注)平屋中門造りは秋田地方を源流とする日本海側東北地方一帯に広がる多雪対応の住居形式で、中門にウマヤと便所を設け、その方面に出入り口をつけたもの